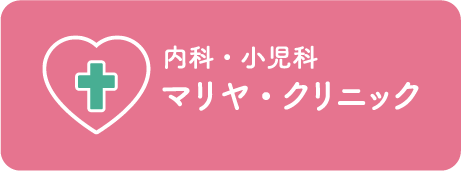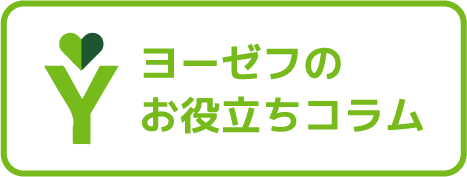ヨーゼフのお役立ちコラム
column
- ホーム
- ヨーゼフのお役立ちコラム
肝腎かなめの腎臓
マリヤ・クリニック・ニュース
2025.10. No.365
異常気象というより地球温暖化が恒常化してきているようですね。また、最近、友人知人、そして多くの方が健康を害して死なれた報告を聞いて心を痛めています。また、政府やニュースの情報を聞いて、警告ばかりなことも気になっています。
ポピュリズムという言葉が多く聞かれます。即自的利益が求められて、これまで形成されてきた価値観や生き方が廃れ、排他的な自己利益追求の考え方が浸透してしまっています。家族間でさえ、助け合うことがなくなり、個々に快楽や富の追及に向いています。「勝ち組」「負け組」などという差別的価値観は異常です。
仕事と稼ぎ優先の社会で、引退ということがどのように捉えられているのでしょうか。スポーツや仕事、地位からの引退は、稼ぐことができなくなったことを意味しています。調べてみると、「定年退職」というのはアジアで多く、人口が多いために一定の年齢になったら退職して若い人に職を与えるためのものだったようです。アメリカやEUでは、年齢を理由にした解雇や退職の強制は違法です。
FIRE(経済的自立と早期リタイア)は欧米の人の理想で、30歳前後から50歳くらいで仕事を持たなくなることがあります。しかし、FIREの失敗例は多くあるようです。他方、無理をせず落ち着いて仕事と生活を営み、90歳を越えても働く人もおります。
私たち夫婦の暮らしを紹介しましょう。食事は殆ど妻が作ってくれます。有害な添加物や素材のある物は食べません。たまには外食しますが、食べ放題や甘味の店には行きません。妻は賑やかな店を怖がります。散歩や運動はなるべく増やします。健康度のチェックと思ってゴルフを月一回ほどします。スコアを気にする人や競争心のある人とはプレーしません。殆ど二人だけです。食料品以外の買い物はあまりせず、必要な物を相談しながら一緒に買います。
私たちの願いは、90歳を過ぎても穏やかに仕事をしながら暮らすことです。夫婦共によく働きますが、疲れたらいつでも寝ます。妻の会話は子供や孫、教会員や患者さんのこと、皆を大事にしています。そして、良く祈り、聖書を読みます。
事務長 柏崎久雄
<肝腎かなめの腎臓>
腎臓は腰の上あたりに左右一つずつある、そら豆のような形をした、握りこぶしくらいの大きさの臓器で、体内の老廃物の排泄、水分量・電解質・血圧の調整、ホルモンの生成などを行う身体の「見張り番」のような働きを担っています。機能が低下すると慢性腎臓病や腎不全に至り、重症化すると透析や腎移植が必要になります。
A.腎臓の構造
腎臓の機能単位をネフロンと言い、ネフロンは腎小体と尿細管を合わせたものです。更に、腎小体は血液をろ過する糸球体とそれを包むボーマン嚢から構成され、尿細管は近位尿細管、ヘンレ・ループ、遠位尿細管に分かれます。
- 1.腎小体
血液中の老廃物や塩分を「ろ過」し、尿として身体の外に排出する働きをしているのが糸球体です。細い毛細血管が毛糸の球のように丸まってできているので「糸球体」と呼ばれます。この糸球体は大体0.1ミリ~0.2ミリほどの大きさですが、1つの腎臓に約100万個の糸球体があります。この糸球体はふるいのような構造をしており、心臓から腎臓に流れ込んできた血液が、この糸球体を通ると、老廃物がふるいを通ってろ過されます。健常な方では、赤血球やタンパク質などはろ過されず、きれいになった血液が、腎臓から身体に戻ります。
ボーマン嚢は糸球体包とも呼ばれ、糸球体を収納した構造をしています。
- 2.尿細管
糸球体でろ過された尿(原尿)は、健常な方では1日におよそ150リットルにもなります。実際の尿は1.5リットル程度ですから、99%は再吸収されることになります。この再吸収する働きをするのが、尿細管です。
糸球体でろ過された原尿には、老廃物以外に、アミノ酸やブドウ糖などの栄養素や、塩分(ナトリウム)やカリウム、リン、マグネシウムなど、さまざまなミネラル(電解質)も含まれています。このような身体にとって必要な成分を再吸収することにより、体内の水分量を一定に保ったり、ミネラルのバランスを調整したり、身体を弱アルカリ性の状態に保ったりすることができるのです。逆に抗がん剤などの薬物には尿細管を通して、体外に排泄されるものもあります。このため、薬物によって尿細管がダメージを受けることもあります。
近位尿細管の上皮細胞の表面部分は密集した微絨毛に覆われ、微絨毛は細胞の表面積を増やし、再吸収の機能を容易にしています。細胞の細胞質には細胞の再吸収活動に必要なミトコンドリアが濃密に保たれています。観察すると、毛細血管に近い近位尿細管は“汚れて”見え、毛細血管から遠い遠位尿細管は“きれいな”外観をしているそうです。ヘンレループは、腎臓の近位尿細管の終端部分から遠位尿細管の始まりの部分までを指し、腎髄質でヘアピンカーブを形成しています。この構造には、尿から水とイオンを再吸収する機能があり、これを実現するために髄質部で対向流交換系が利用されています。
B.腎臓の働き
- 1.体液調整
腎臓は老廃物(尿毒素)や過剰に摂取しすぎた塩分や水分を排泄し、体液を一定に保つ機能を司っています。
腎の表層側(皮質)には糸球体があり、血液中のタンパク質より小さな物質は水分とともに尿細管という細い管に向けて原尿として漏れ出ます。尿細管は複雑なヘアピンカーブのような折り返しが2カ所あり、細長い管を上下する間に、原尿から生体に必要なものだけを再吸収し、伴走する血管に戻していきます。結果として、栄養素(ブドウ糖やアミノ酸など)やミネラルは必要な量だけ回収され、老廃物や過剰な物質はそのまま尿細管を通過して、最終的には尿となります。この機能を発揮するために、腎臓は1分間に1リットルもの血液を受け入れ、尿となるのはわずか一日で1.5リットル程度です。一見、非効率にも感じられますが、腎臓は「生体に必要なものでも一旦ろ過して、選択的に再吸収する」という確実な方法によって体液恒常性を維持しています。
- 2.ホルモンの生成・分泌
腎臓には老廃物を体外に排出する他に、生体恒常性の維持に関わる各種ホルモンを産生する役割があります。腎臓の間質で作られるエリスロポエチンは、赤血球の前駆細胞に働きかけ、赤血球の産生を亢進させます。慢性腎臓病が進行すると、エリスロポエチンの産生が不十分となり、貧血になります。これを腎性貧血と言います。また、カルシウムとリンの吸収に関与するビタミンDは腎臓で活性化されます。慢性腎臓病が進行すると、ビタミンDを活性化することができず、骨がもろくなり、骨やミネラルの代謝異常をきたします。さらに、腎臓の傍糸球体装置と呼ばれる部分ではレニンという血圧調節ホルモンが分泌されます。このホルモンは血圧上昇作用を持つアンジオテンシンIIという物質を作ります。動脈硬化などにより腎動脈に狭窄があると、腎臓への血流が低下するために、レニンの産生が亢進し、高血圧となり、これを腎血管性高血圧といいます。
- 3.その他の腎臓の働き(骨など)
腎臓は身体の水分の量や体液中の様々なミネラルの濃度を調整する働きをしています。腎臓が適切にそれぞれのミネラルを調整できるように、骨は体内にあるカルシウムの99%以上、リンの85%、マグネシウムの60%、ナトリウムの30%を貯蔵しており、必要に応じて体液への出し入れを行っています。また、腎臓は、骨やミネラルを調整する活性型ビタミンDを産生したり、副甲状腺ホルモンやFGF23などの液性因子の刺激をうけてミネラルの再吸収を調節したりしています。健常な方では腎臓と副甲状腺と骨で微妙な調節が働いていますが、腎臓の働きが低下すると、制御を失った骨や副甲状腺は代謝が暴走し始め、多様な骨ミネラル代謝障害を呈します。この病態は慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常(CKD-MBD)と呼ばれ、主に透析患者さんでは深刻な問題となっています。
C.腎臓の病気と症状
腎臓病は初期段階では自覚症状がほとんどないことが多く、むくみ、尿量の変化、腰や背中の痛み、高血圧などから気づくことがあります。高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満などは腎臓病を悪化させるため、しっかりと治療することが重要です。
- 1.慢性腎臓病
腎機能が慢性的に低下した状態の総称で、3ヶ月以上タンパク尿が出たり、腎機能の指標である糸球体濾過量が基準値以下に低下したりすると診断されます。
心血管系疾患と互いに悪化要因として作用し、認知機能の低下、骨粗しょう症、骨折、サルコペニア(全身の筋肉量と筋力が低下する状態)、フレイル(虚弱)などを招いてQOLの低下や生命予後を悪化させます。
- 2.急性糸球体腎炎
多くの場合A群β溶連菌などの感染後に10日前後の潜伏期間を経て発症します。一般的に小児~若年者に多いですが、成人や高齢者でも時々見られます。
- 3.慢性糸球体腎炎
糸球体に炎症が起き、慢性的に腎機能が低下していく病気で、慢性腎臓病の原因の一つです。
- 4.ネフローゼ症候群
尿に大量のタンパクが漏れ出てしまうことで、血液中のタンパクが減り(低タンパク血症)、むくみが生じる病気です。
- 5.腎不全
加齢に伴い、ネフロン数が減少し、その機能も衰えて予備力が低下していきます。それでろ過圧を上げることでろ過量を維持しようとしますが、残存ネフロンの負担が増えて腎機能の低下を招きます。腎臓の機能が低下した状態で、急激に悪化する「急性腎不全」と、徐々に悪化する「慢性腎不全」があります。
- 6.腎盂腎炎
膀胱炎などの細菌が腎臓に達して炎症を起こす病気です。
- 7.腎結石・尿管結石
腎臓や尿管に結石ができる病気で、腹部や背中の痛みを引き起こすことがあります。
- 8.腎臓癌
腎臓にできる悪性腫瘍です。結石や腎臓癌では血尿を起こすことも多いです。
D.腎臓疾患の予防
- ● 肥満者は減量する。適度な運動を心掛ける。喫煙を止める。
- ● 塩分を控える。過度には控えない。
- ● 腸内環境の悪化を防ぐ。抗酸化対策。抗炎症対策。
- ● 貧血を改善させる。
- ● 高血圧、タンパク尿、糖尿病の治療
- ● 適切な水分補給
E.人工透析
人工透析は、腎臓の機能が低下した際に、老廃物や余分な水分を人工的に取り除く治療法です。腎不全などが原因で腎臓の働きが不十分になった場合に行われます。
- 1.血液透析
体外に血液を取り出し、ダイアライザーと呼ばれる人工腎臓のフィルターを通して、老廃物や水分を除去します。
- 頻度: 通常、週に2~3回、医療機関に通院して行います。
- 時間: 1回の治療には4~5時間程度かかります。
- 特徴: 医療スタッフに任せられる一方で、通院の時間的拘束があります。
- 2.腹膜透析
自分のお腹の中にある腹膜を利用して、透析液を注入・排出することで老廃物や水分を取り除きます。
- 頻度: 自宅や外出先で、1日に数回、透析液を交換します。
- 通院: 月に1〜2回程度の通院で済みます。
- 特徴: 自分のライフスタイルに合わせて行える反面、自己管理が必要です。
- 3.費用と医療費助成
1ヶ月の透析治療の医療費は、患者一人につき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。人工透析は高額な治療費がかかりますが、患者さんの経済的負担を軽減するための公的助成制度があります。
- 4.人工透析と日常生活の注意点
人工透析を受けながら健康的な生活を送るためには、以下の点に注意が必要です。
- ● 塩分・水分の制限。
- ● カリウムを多く含む食品(果物や野菜など)の過剰摂取を避ける。
- ● シャント(血液透析で使う血管)を大切にする。
執筆者の紹介
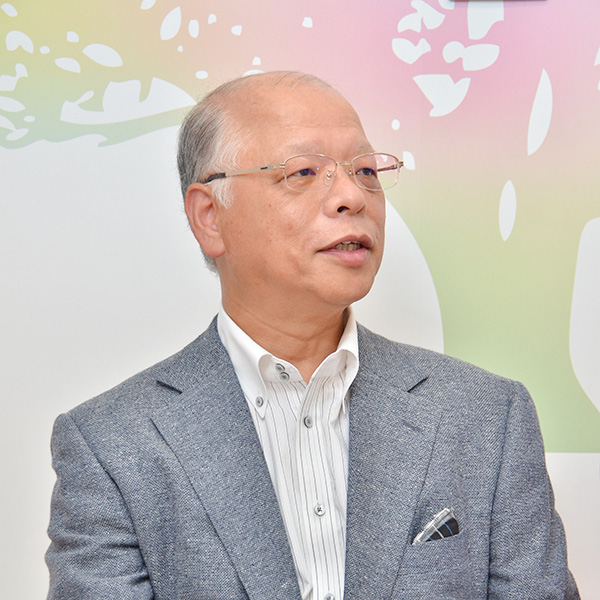
柏崎 久雄
・株式会社ヨーゼフ 代表取締役社長
・マリヤ・クリニック 事務長
・千葉福音キリスト教会 牧師
妻(マリヤ・クリニック院長)が低血糖症なのをきっかけに、分子整合栄養医学を勉強し、2004年にサプリメント会社を設立