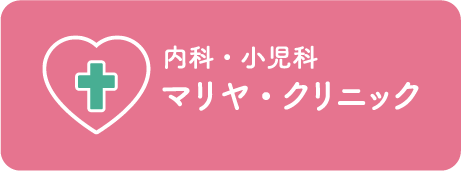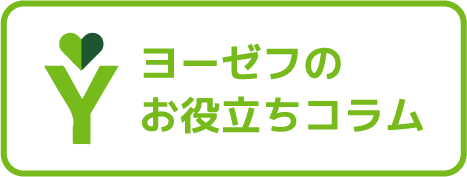ヨーゼフのお役立ちコラム
column
- ホーム
- ヨーゼフのお役立ちコラム
肝腎要
マリヤ・クリニック・ニュース
2025.8. No.364
暑い夏はまだ続きそうですね。線状降水帯の怖さと頻発には驚いています。夏休みには旅行に行くということが誰しも恒例でしたが、旅に出ることも怖くなってきました。海外旅行も行く気がしません。アメリカの物価高騰には怖気づきますし、世界中の治安の悪化も心配です。中国や韓国の不景気もひどくなっています。世界中が天候異変、景気悪化、戦争、治安、物価高騰などで、不安定になっています。安全そうで安価な日本に観光客が殺到しているのでしょう。
(株)ヨーゼフのショッピングサイトが8000回以上の不正アタックでクレジットカード決済が使えなくなりました。対応に追いまくられています。マリヤ・クリニックも開業38年にして初めて赤字になりました。医療機関はIT対策や人材不足もあり、経営が難しくなっています。医療機関の廃業・倒産が過去最高だったと報道されています。ネット・IT対策は経費と人材が必要で、政府の一方的な指導も閉院を促していると言われています。
当院・当社はまだ余力がありますが、企業経営はこのようにして淘汰されていくのでしょう。これからは学歴や頭の良さは役に立たない時代になっていき、対応力や知恵、そして気力が必要になるでしょう。消費経済の中で甘やかされて育った世代に、これらの弱肉強食の世界的難関への対応ができるのでしょうか。日本社会は、混乱と崩壊の道に歩むことになりそうです。
そういう面で健康管理の不十分さが気になります。医療費も薬代も高騰し、医療機関も急激に減ることが予想されます。安易かつ美食志向の食生活は、間違いなく健康を害します。今月は肝臓についてまとめました。原材料名に「果糖」とあるものは摂らないでください。ハムやソーセージに発色剤として含まれる「亜硝酸ナトリウム」は、致死量2gの劇薬です。マーガリンなどに含まれるトランス脂肪酸を含めて、政府は「少量だから安全」としていますが、人の命を犠牲にした商業主義です。そのようにして人の命を軽視して経済的繁栄を目論んできた社会が壊滅しようとしています。残念ながら、政府も企業も信用できなくなっています。それはもっとひどくなるでしょう。自己管理を怠ってはいけません。
事務長 柏崎久雄
<肝腎要>
最も大事な大切なこと、という意味で「肝心かなめ」とも書かれます。身体にとって肝臓と腎臓と心臓が「かなめ」な大事なことなのです。今月は、肝臓についてお伝えします。
肝臓は、右側の肋骨の下、腹腔と呼ばれるお腹の中に位置しています。重さは0.9~1.4kgあり、体のなかで最も大きな臓器です。肝臓は体内で非常に多くの複雑な化学変化を行っており、様々な物質の生産や変換、貯蔵、分解、排泄といった多岐にわたる働きを担っています。このため、肝臓の健康は体全体の健康にとって非常に重要です。
1.肝臓の血管
- ① 肝動脈:心臓から酸素を豊富に含んだ血液を肝臓に運びます。
- ② 門脈:腸で吸収された栄養分や老廃物を含んだ血液を肝臓に運びます。
- ③ 肝静脈:肝臓で処理された血液を心臓に戻す役割を担います。
肝臓は肝動脈と門脈で血液を供給する仕組みによって保護されていて、仮に片方の血管が損傷したとしても、もう一方の血管から流れてくる血液から酸素と栄養素を得ることができるため、肝臓は機能を維持することができます。但し、門脈は栄養分と共に腹部臓器を巡った代謝物・老廃物も流入するため、がんが転移されやすいのです。肝臓は毎分およそ1.5リットルの血液が運ばれてきて、血液供給の半分以上を静脈に頼っているただ1つの臓器です。肝臓は大量の血液を貯留していて、循環血液量の調整にも寄与します。
肝臓に入った血液は肝静脈を通って出ていきます。その血液は門脈からの血液と肝動脈からの血液が混じり合ったものです。肝静脈の血液は下大静脈(全身で最も太い静脈)に流れ込み、下半身と腹部から上がってきた血液とともに心臓の右側部分に送られます。
血管の他に、肝臓内で作られる胆汁を腸まで運ぶ胆管という管もあります。
2.肝臓の働き
- ① 代謝機能:糖質、脂質、タンパク質などの栄養素を分解・合成し、エネルギー源として利用したり、体内で必要な物質を作り出したりします。
肝臓は、食事による大量のグルコースをグリコーゲンに合成して保存し、空腹時にはそのグリコーゲンをグルコースに戻すことで、血糖値の急激な上昇と低下を防いでいます。更に、アミノ酸をグルコースに変換(糖新生)して補充もします。グルコースを原料にグルコサミンなどを合成することもします。
血漿タンパク質の殆どを合成・分泌し、アミノ酸を貯蔵し、アミノ酸に由来するアンモニアを無害化します。コレステロール、リン脂質、中性脂肪を合成し、余分なコレステロールを胆汁酸に変換して胆汁にします。空腹時には、脂肪酸からケトン体を合成分泌して栄養源にします。
- ② 貯蔵機能:余分な糖質をグリコーゲンとして貯蔵し、必要に応じてエネルギー源として放出します。また、ビタミンやミネラルなどの栄養素も貯蔵する役割があります。
エネルギー以外には、赤血球を作る際に必要な鉄やビタミンB12も肝臓に貯蔵されています。ビタミンAやD、亜鉛も肝臓で貯蔵される栄養素です。これらも必要に応じて肝臓から供給されます。
- ③ 解毒・排泄機能:アルコールや薬物、老廃物などの有害な物質を分解し、無毒化して体外に排泄する働きがあります。
肝臓は、身体にとって有害な物質を無毒化したり、そのままでは排泄できない物質を排泄可能な形に変換したりする働きも担います。アルコールやニコチン、治療薬の成分などを分解・無毒化するのも肝臓です。
体内でできる有害物質や排泄困難な物質なども、多くが肝臓で処理されます。たとえば余分なアミノ酸を分解する過程でできるアンモニアは、そのままでは有毒なので、尿素に変換されます。赤血球が分解される際に出るビリルビンを、水に溶ける形に変換するのも肝臓の役目です。体内で働いたホルモンも、一部は肝臓で分解されます。
また、体内に乳酸が余分に溜まると倦怠感を自覚するといわれていますが、肝臓では乳酸をブドウ糖に変換できます。
- ④ 免疫機能:免疫細胞を活性化させたり、サポートする役割も担っています。
肝臓は、腸管由来の外来細菌やその菌体成分と代謝物にも対処します。消化管から来る血液の通り道には、クッパー細胞と呼ばれる免疫細胞が常駐し、栄養素と一緒に入ってきた細菌やウイルスなどの異物を除去しています。ほかにも、ウイルスに感染した細胞や老廃物を処理するナチュラルキラー(NK)細胞など、免疫系の細胞が多く存在します。
また、免疫系が適切に働くには、病原体に結合して目印となる免疫グロブリン(タンパク質)が欠かせません。免疫グロブリンは免疫細胞が作りますが、そのためには肝臓から供給されるアミノ酸やエネルギーが不可欠です。
- ⑤ 胆汁の生成と分泌機能:脂肪の消化を助け、吸収を促進する働きを持っている胆汁という黄色の液体の生成と分泌を行います。
胆汁には脂肪の消化・吸収を助けるだけでなく、肝臓の持つ解毒作用と協力し老廃物を体外へ排泄する働きも持っています。例えば古くなった赤血球が役目を終え破壊されると、ビリルビンという色素が分解の過程で生じます。肝細胞はこのビリルビンを水に溶けやすい形にして胆汁中に排出しています。最終的に、消化管中に分泌され便とともに体外に出て行きます。また、コレステロールも最終的には肝臓から胆汁を介して体外へ排泄されます。
3.肝臓の悪化による影響
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、働きが悪化しても目立った症状はなかなか現れません。
- ① 全身がだるくなって疲れやすくなる
ブドウ糖の供給を調節する機能が低下して、全身の細胞がエネルギー不足の状態になります。有害物質の解毒・分解が滞ることで、アンモニアなどの老廃物が身体にたまることも倦怠感の一因です。ほかにも栄養素の貯蔵障害や、タンパク質の合成低下、ホルモンの分解が滞ることによるホルモンバランスの乱れも影響します。このように、肝臓のさまざまな機能の低下が、全身のだるさや疲れやすさにつながります。
- ② 黄疸(肌や目が黄色くなる)やむくみが出やすくなる
黄疸とは、白目や皮膚が黄色くなる症状です。これは肝機能の低下を示す特徴的な症状で、肝臓におけるビリルビン(赤血球が壊されるときに出てくる黄色い色素)の代謝と排泄がうまくいかなくなると起こります。急性肝炎の場合は、黄疸が出現する数日前から、尿の色が茶色くなる症状も現れるのが一般的です。
むくみの原因は、肝臓におけるタンパク質の合成障害かもしれません。血液中のタンパク質(アルブミンなど)が減少すると、水分を血管内に保持する力が弱まります。すると水分が血管外に漏れ出し、むくみや腹水として溜まってしまうのです。
- ③ 更に悪くなると
急性肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝炎、非アルコール性肝炎、ウイルス性肝炎、肝硬変、肝臓がん、などの重大な病気に進展していきます。
4.脂肪肝
脂肪肝は、中性脂肪が肝臓に多く蓄積した状態ですが、明らかな自覚症状が現れにくい状態です。脂肪肝が進行して初めて食欲不振やだるさなどの自覚症状が現れるようになります。
脂肪肝の状態が進行すると、肝炎や肝硬変、肝がんなどの病気を発症することがあります。これらの病気が悪化するとむくみや黄疸、腹水などの症状が出現します。また、肝臓への血液の流れが滞るようになると、胃や食道を通る静脈に血液が流れて静脈瘤とよばれる瘤が形成され、破裂すると大量出血をきたす場合もあります。
脂肪肝は進行すると重篤な症状が現れる可能性がある状態です。無症状であっても、健康診断などで指摘された場合は放置せず治療を受けましょう。また、脂肪肝の患者は、心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすいことが知られており、心血管系の病気に対しても注意が必要です。
- ● 飲酒量が多い人に起こるアルコール性肝疾患
アルコール性肝疾患はお酒の飲みすぎによって生じます。
- ● アルコールを摂取していないが生じる非アルコール性脂肪性肝疾患
肥満やメタボリックシンドロームなどを原因として生じるといわれています。そのほか、やせ過ぎ、薬剤、遺伝性代謝疾患、妊娠といった特殊な原因によって脂肪肝が生じることもあります。
- a. 肝臓に慢性的な炎症が持続することで肝臓が硬くなる線維化を経て肝硬変へと進行する非アルコール性脂肪肝炎
- b. 線維化がなく肝硬変へ進行しない非アルコール性脂肪肝
10〜20%が非アルコール性脂肪肝炎、80~90%が非アルコール性脂肪肝です。
- ① 運動療法
脂肪に溢れた肝臓から中性脂肪を除いていくには、ゆっくりとした運動を長い時間続けて肝臓にあるグリコーゲンを消費した上で中性脂肪の燃焼まで持っていかなければなりません。肥満は、代謝(エネルギー消費)を鈍くするため、ウォーキング、ジョギング、スイミングなどを続けることが大事です。
- ② 食事療法
唐揚げや天ぷらなどの油物、ベーコンや加工食品などの保存料・添加物などが多い物、アルコールはできるだけ摂取を控えましょう。清涼飲料水には、糖分が多量に含まれているので飲まないようにしてください。果物ジュースも同様です。
果糖の含まれている食品が多くなっていますが、果物由来のものではなく安価に造られるからです。果糖は肝臓以外では代謝できないので、蓄積しやすく、老化物質(AGEs)の原因となる糖化反応を起こしやすいのです。果物でも食べ過ぎには注意しましょう。
食べるべきものは、低脂質・低糖質のものであり、野菜、海藻、豆類、魚などが良いでしょう。ゆっくり食べることも大事です。抗酸化作用のある緑黄色野菜をしっかり摂りましょう。
- ③ 睡眠、休むこと、横になること
肝臓が悪くなると横になりたくなり、休みたくなります。横になると肝臓への血流が増え、肝臓の負担を減らします。睡眠により、さらに身体の毒素を排斥する肝臓の働きを助けます。睡眠不足は、肝臓を傷めていきます。
- ④ サプリメント
ビタミンE、カルニチン代謝を促し脂肪酸代謝を促すビタミンC、肝臓から脂肪の排泄を促進する抗脂肪肝因子であるイノシトールが有効です。肝臓の繊維化(肝硬変)を防ぐためにはビタミンAが役に立ちます。
5.感染による肝炎
C型肝炎、B型肝炎、A型肝炎、E型肝炎などがあり、それぞれウイルス感染によって発症します。血液を介して感染し、輸血や血液製剤、そして注射針の使い回しによって感染することがあったので、現在は対策が取られ、政府による賠償がされることもあります。慢性感染を経て肝硬変になることも多くありました。A型肝炎とE型肝炎は、不衛生な水・生野菜・魚介類によって感染していました。B型肝炎とC型肝炎の治療にはインターフェロンが用いられ、A型肝炎は自然経過、E型肝炎も安静と対症療法が主です。
薬剤性肝障害もあります。肝臓は、薬物が最初に通過する臓器なので、薬物による障害を受け易いのです。
執筆者の紹介
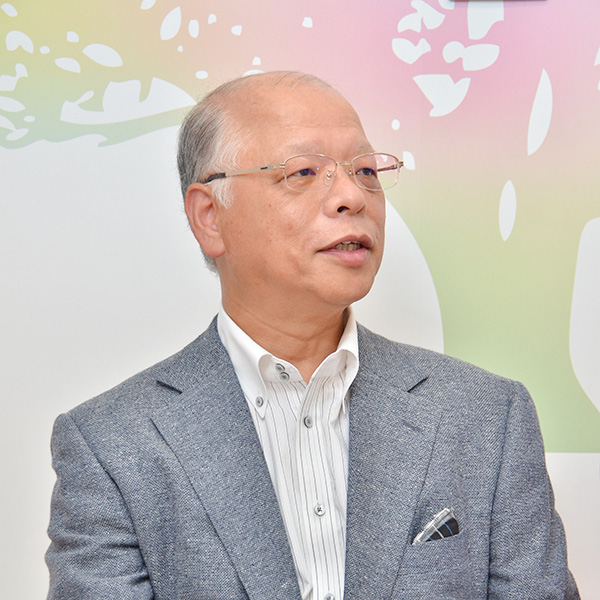
柏崎 久雄
・株式会社ヨーゼフ 代表取締役社長
・マリヤ・クリニック 事務長
・千葉福音キリスト教会 牧師
妻(マリヤ・クリニック院長)が低血糖症なのをきっかけに、分子整合栄養医学を勉強し、2004年にサプリメント会社を設立