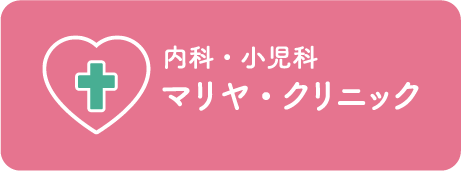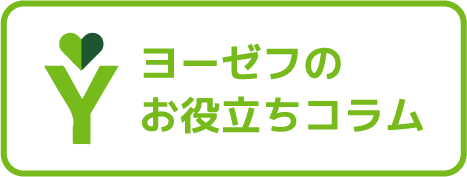ヨーゼフのお役立ちコラム
column
- ホーム
- ヨーゼフのお役立ちコラム
肥満は身体を大きく損ないます
マリヤ・クリニック・ニュース
2025.8. No.364
夏には故郷を想い出します。前橋市は赤城山が近いので、夏には夕立と雷が殆ど毎日あり、一軒隣に雷が落ちた時は驚きました。夕食が終わってくつろいだ時に、真ん中の電灯から下に雷が目の前を走ったそうです。暑い夏を遊び歩いていた小学時代、熱中症などという言葉はありませんでした。キュウリに味噌を付けて何本も食べ、スイカは縁側に座って種を飛ばしあっていました。
この夏は畑にキュウリ、トマト、ナス、枝豆、トウモロコシ、ブルーベリーがなって、収穫を楽しんでいます。妻は大喜びです。ジャガイモは50kgほど穫れました。猪除けにブロックや網で囲いを作ったのですが、鳥が啄むことは想定外で、上に針金を張り巡らせてキュウリやトマトの柵を上から吊りました。カボチャは2mの囲いを乗り越えて蔓を伸ばしています。生きている充実感を感じます。
熱中症警戒アラートが飛び交っています。確かに注意するべきですが、外出を全くせずに室内でエアコンをかけて過ごすことが健康に良いのでしょうか。コロナ警戒のワクチン接種騒ぎを思い出します。先導していた尾身元会長が「感染を防ぐ効果はあまりない」「若い人は感染しても重症化しない。」などと発言しています(2025.6.20. )。
注意警戒を呼び掛けたことで責任を全うしていると考えている行政を信じてよいのでしょうか。私たちは、コロナワクチン接種の害を訴えて、その記事はネットから強制的に削除されました。ワクチンの被害者はかなりの数になっていますが、立証責任を求められて泣き寝入りです。その害は免疫機能の衰えに結び付くとお伝えしています。
子供たちへも注意や警戒を要求して、外で遊ぶ子は殆どいなくなりました。自ら注意し、調整することができなくなっているようです。今後、災害や異常気象、その他多くのことが起こると予想されます。政治も経済も世界的に流動しています。AI化が進んで、事務職は減少し、過去のエリート教育は無駄なものとなってくるでしょう。注意警告で済ますのではなく、自己判断と自己管理が必要な社会となってくると思います。言われたことを守る日本の国民性が、個々の人を不幸にするのではないかと心配します。
事務長 柏崎久雄
<肥満は身体を大きく損ないます>
巻頭言にも書いたように、健康に留意し自己管理をする人が少なく、人や行政、或いは医師から注意警告されなければならないようです。医師から厳しく言われても、薬をきちんと服用せず、余ってしまう人もおります。健康は薬以外に、食事や運動、生活のリズム、その他多くの要素によって成し遂げられます。暑いからといって外に出ず、エアコンの効いた室内で毎日を過ごしていたら、自律神経は損なわれ、免疫力も落ちてきます。
世界的に子供たちが甘やかされて育ち、糖分過剰摂取や運動不足も重なって肥満児が急激に増えています。大人も同様です。堅い食物をよく噛んで食べることも減り、甘く柔らかな食物が流行っています。糖分の多い飲料水は身体にとって毒であり、ジュースなども糖分の吸収が速いためインスリンが過剰となり、脂肪が身体に溜まってくるのです。
体脂肪が異常に多く蓄積された状態が肥満です。糖尿病、脂質異常症、高血圧、胆石症などの生活習慣病につながるばかりでなく、がんのリスクも高めます。脂肪細胞の数は、思春期を過ぎて身体の成長が止まるとそれ以上は増えなくなり、減量しても脂肪細胞の数は減りません。脂肪細胞に脂肪がたまりその体積が170%以上にふくらむと、脂肪細胞の数が増加し始め、さらに肥満が進みます。
身体に蓄えられる脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があります。皮下脂肪は皮膚のすぐ下に蓄えられる脂肪です。皮下脂肪は女性に多く、ヒップや大腿部につきやすく下半身肥満(洋梨型肥満)を起こしやすいです。一方、内臓脂肪は肝臓や腸などの臓器の周りに蓄えられる脂肪(腹腔内脂肪)です。男性に多くみられ、ヒップよりウエストの方が大きい上半身肥満(りんご型肥満)を引き起こします。生活習慣病につながる危険が大きい肥満です。内臓脂肪型肥満は生活習慣病を合併することが知られています。現在そのような病気を発症していなくても、肥満の状態が続けば将来に発病する危険性が高いと考えなければなりません。
1.肥満と合併症
- ●糖尿病
インスリンが多く分泌されると肥満になりやすく、肥満はインスリン抵抗性の原因となるなど、糖尿病と肥満は深い関係があります。
- ●脂質異常症
肥満は中性脂肪が増えている状態でもあります。中性脂肪が増えると、HDLコレステロールが減りLDLコレステロールが増え、脂質異常症になるリスクが高まります。
- ●脂肪肝
余分な中性脂肪は肝臓に貯蔵されると、脂肪肝の原因になります。脂肪肝は肝硬変や肝臓がんにつながる可能性があります。
- ●ホルモンバランス異常
肥満によりホルモン分泌に変調をきたし、無月経や二次性徴が始まらない、前立腺が肥大するなどの症状が起こることがあります。
- ●がん
過体重と肥満が、がんのリスクを高めることが疫学調査で知られています。肥満と診断されたら、がんを予防するためにカロリーの総摂取量を減らすことが大切です。
- ●老化
肥満の人は、そうでない人に比べて「命の回数券」と呼ばれる、染色体の末端にあるテロメアの長さが短くなりがちです。つまり老化が早く進むことがわかってきました。LDLコレステロールなどにより身体が酸化しても、テロメアは短くなります。
※ メタボリックシンドローム
内臓脂肪型肥満に、脂質異常、高血糖、高血圧のうちいずれか2つ以上を併せ持った状態をメタボリックシンドロームと呼んでいます。脂質異常症、糖尿病、高血圧はどれか一つを発症すると他を合併しやすく、それぞれの症状は軽度であっても、多く合併するほど動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳卒中などの心血管病変(虚血性心疾患)や脳梗塞のリスクを高めます。どれか一つ症状があると心血管病変を併発するリスクが5倍、2つ持つ人は10倍、3つとも揃うとなんと35倍に上昇してしまうといわれます。
さらに怖いことには、これらの病気は「サイレントキラー」とも呼ばれ、症状が目に見えない形で進行するのです。治療を受けずに放置するうちに重大な病気を引き起こしてしまう可能性が高く、「気づいたときには手遅れ」ということも少なくありません。
2.肥満の原因
- ●摂取カロリーが消費カロリーを上回る
私たちが食事から摂取したカロリーは、エネルギーとして消費されますが、消費しきれないものは、身体の中で脂肪(体脂肪)として蓄えられてゆきます。肥満は、摂取カロリーが消費カロリーを上回ることが原因で起こります。基礎代謝は、35歳を過ぎると急速に低下し、それまでと同じ食事を摂っても、身体が消費できるカロリーは少なくなります。
- ●食欲中枢の不調律が深く関与
食べ過ぎて、摂取した余分なカロリーを蓄積するために、体内の脂肪細胞に貯める脂肪の量が増え、それぞれの脂肪細胞が太り、肥満の状態になります。
- ●インスリン過剰分泌
血糖値を下げるホルモンであるインスリンは「太らせるホルモン」とも呼ばれます。肝臓や筋肉中のグリコーゲンの合成を促進しますが、脂肪の合成を促進するとともに脂肪の分解も抑制するため、インスリンの過剰分泌は内臓(肝臓など)や皮下に脂肪を貯め肥満の原因となります。
※ インスリン抵抗性と肥満の関連性
- ① 肥満者は脂肪細胞に含まれる中性脂肪の量も増えて、そこからインスリンの作用を阻害する物質(TNF-αなど)を多く分泌しているといわれています。
- ② 肥満になると脂肪により細胞自体が大きく膨らみ、インスリンの感受性が鈍くなり、インスリンレセプターの数も減ります。
- ③ 過食により血糖が増え過ぎてインスリンの量が相対的に足りなくなります。また肥満者には体質的に血糖の量に応じてインスリンの分泌量を増やせない人が多いようです。
- ④ 糖尿病患者では血液中のGTF(グルコース・トレランス・ファクター…血糖値を正常に保つために働く耐糖能因子)が低下しているため、インスリンが過剰に分泌されやすいと考えられます。
- ●満腹中枢と摂食中枢の機能が不調律
脳の視床下部には、食欲を調節する作用があり、なんらかの原因で調節がうまくいかなくなると、過食が起こり肥満の原因となります。食欲中枢に関わる要素には次の項目があります。
※ 食欲中枢と肥満の関連性
- ① 低血糖状態により刺激
血糖上昇は満腹中枢を刺激し、低血糖状態は摂食中枢を刺激します。食後でも血糖値が下がると、また食欲がわいてしまいます。野菜などを一緒に食べておくと良いでしょう。
- ② ホルモン
ホルモンと食欲は深く関わっており、ノルアドレナリン、インスリン、ステロイドホルモン(副腎皮質ホルモン、プロゲステロン)、甲状腺ホルモンは摂食を刺激し、グルカゴン、エストロゲンは反対に低下させます。セロトニンはノルアドレナリンの作用を抑え過食を防止します。
- ③ 胃の容量
胃壁にある副交感神経の受容器が胃の膨張度を感知して、その信号を視床下部にある満腹中枢に伝えます。摂食を抑える要素として、食事のボリューム感も関与します。例えば、胃の中で容量が増大する海藻(昆布、わかめ)などの水溶性食物繊維や不溶性食物繊維を摂ることで、満腹中枢が刺激され、過食を防ぐことができます。
- ④ 自立神経失調症
食欲中枢のある脳の視床下部には自律神経の中枢があり、食欲は自律神経の影響を受けます。
- ④ ストレス
ストレスは自律神経に変調をもたらします。
- ① 低血糖状態により刺激
- ●食欲を調節する生理活性物質の減少
γ‐リノレン酸は食べたものを燃焼させる働きを促し、食欲をコントロールする作用があります。γ‐リノレン酸の濃度が低下する要因として、加齢、女性の生理前後、飲酒、ストレス、細菌感染、発がん物質、栄養素の不足(亜鉛、マグネシウム、ビタミンB6、ビオチン、ビタミンC、ナイアシンなど)があり、過食の一因となります。
- ●代謝の障害、酵素の活性度の低下
脂肪を燃焼させたり、貯蓄、分解する過程を調節したりする酵素の障害も肥満の原因となります。例えば、TCAサイクルでの酵素活性、脂肪酸をミトコンドリアに運ぶためのアシルカルニチンを生成するはたらき、脂肪酸を脂肪組織に運び、脂肪化するはたらきを活性化する酵素の調節機能などに関与します。
- ●エネルギー消費の低下
基礎代謝の低下、運動不足、食事を消化吸収するためのエネルギー不足、褐色脂肪細胞(注)から生成される熱量の低下などにより、エネルギー消費は低下します。
(注)褐色脂肪細胞は、過食時にエネルギー消費を増大する機構がありますが、肥満者はこの食後の熱産生が普通の人より少ないようです。
3.肥満対策=食事の見直しと運動が二本柱
- ●1日の総カロリー摂取量を減らす
- ●栄養のバランスを考える
炭水化物は複合糖質(穀類)から摂ることをこころがけ、単純糖質(砂糖、はちみつなど)は控えます。糖質は余分に摂ると脂肪に変わり、体内に貯蔵されてしまいます。また、過剰な糖分摂取は脂肪の合成を促進するインスリンの分泌を刺激しやすいのです。ただし炭水化物が総摂取エネルギー量の40%以下になると脂肪異化、タンパク質の異化が起こりやすくなり、身体の代謝を損ねます。熱量の比で「炭水化物:脂質:タンパク質=5:2:3」の比で摂るのが理想的です。
- ●タンパク質は一日で標準体重×1.14g以上を目安に摂取する
食事制限を始めると、タンパク質不足に陥りがちですが、基礎代謝を落さずに健康的に減量するためには、タンパク質の摂取は必須です。ただし、動物性タンパク質は脂肪も同時に摂ることになり注意する必要があるため、プロテインパウダーの利用をお勧めします。
- ●ビタミン、ミネラルを多く摂る
野菜をたくさん食べるようにします。1日350g以上は必要です。野菜は生よりも、加熱すると水分が減り、かさが減って多く食べることができます。
- ●運動による減量
食事の制限や工夫による減量は可能ですが、身体を維持するための適切な栄養を摂り、かつ基礎代謝を高めるために、運動は不可欠です。食事制限による減量だけでは筋肉が落ち、糖代謝などの障害がさらに悪化し、脂肪は減らないという悪循環に陥ります。たるみやしわにならずに脂肪を減らすためにも、適切な運動が有用です。運動により血流が良くなって、動脈硬化や血栓の予防にもなります。インスリンの感受性が向上して血糖値も安定し、自律神経も強化されます。
※ 今回の原稿は「新・栄養医学ガイドブック」(柏崎良子著)を参考にしました。
執筆者の紹介
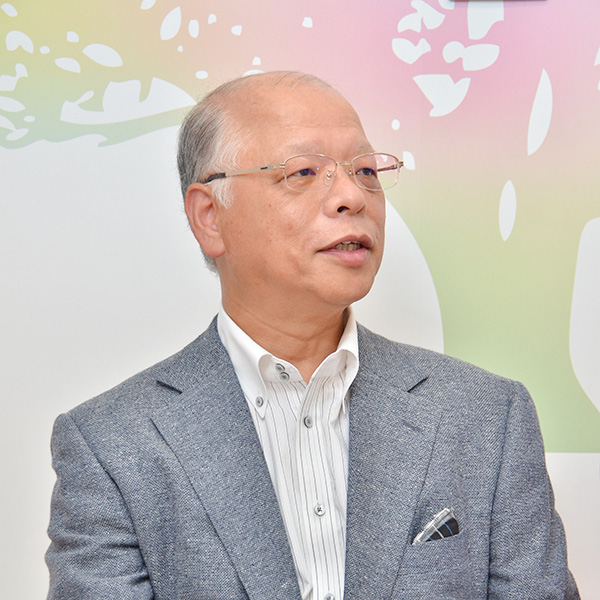
柏崎 久雄
・株式会社ヨーゼフ 代表取締役社長
・マリヤ・クリニック 事務長
・千葉福音キリスト教会 牧師
妻(マリヤ・クリニック院長)が低血糖症なのをきっかけに、分子整合栄養医学を勉強し、2004年にサプリメント会社を設立