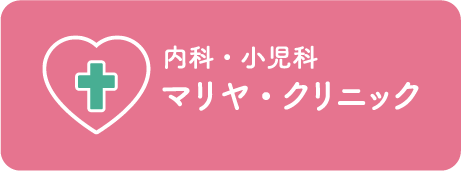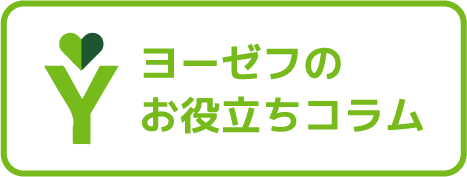ヨーゼフのお役立ちコラム
column
- ホーム
- ヨーゼフのお役立ちコラム
暑さに負けないために
マリヤ・クリニック・ニュース
2025.7. No.363
今年の夏も暑いのでしょうが、日本は四季折々に気候が変動するので、暑さ対策ばかりではありません。それで、日本人は天候の話題が多いですね。気候の変わらない国に行って、「今日は良い天気ですね。」と話すと変に思われます。
世界的には戦争や紛争、難民問題、物価高、犯罪、など問題が山積みです。夫婦でかなり多くの国に旅行してきましたが、コロナ以降、治安が悪くなり、海外旅行は諦めています。アメリカでも、子供を家に一人にすることや、外出させることは禁じられています。子供がトイレに行くときは、親は外で待っていなければ罰せられます。大人でも、荷物から離れたらすぐに持っていかれます。ある国では、歩いていて車に轢かれたら歩行者の責任とも言われました。
インバウンド(外国人が訪日すること)がもてはやされていますが、そんな安全な日本に犯罪が増えています。外国人を嫌うわけではありませんが、平和や安全に慣れた日本は犯罪者にとっては絶好な国です。そして、日本人もまた安易に騙されて犯罪に加担しています。
国際化とは、そういうものです。国際水準で見れば、物価は間違いなく上がるでしょう。零細企業が多く、中流家庭が殆どだった日本社会の貧富の差は大きくなるでしょう。真面目に働けば、良い暮らしができる時代は去っていきます。学歴重視の落ち着いた社会は崩壊し、生き抜く力を持っていなければ家族を養えなくなり、結婚も出産も減っていきます。慣例に縛られた政治は社会と世界に対応できなくなり、不満と欺瞞が高まってきます。大企業も潰れます。
個人の飲食店、居酒屋が急激に減っています。そのようなことに費やす金が乏しくなっているのです。娯楽やスポーツに費やす額も減り、子供の減少により教育産業も衰え、高齢者の介護をする人も足りなくなります。医療機関も、保険収入が減らされて赤字経営が多くなり、閉院する診療所が増えています。
もはや、甘えて生きられる時代ではなくなりつつあります。自己管理をしっかりとし、家族の結び付きを強くし、助け合える仲間を増やしてください。
事務長 柏崎久雄
<暑さに負けないために>
今年の夏も暑そうです。もう一度、暑さ対策を考えてみましょう。
身体の体温調節機能は、汗をかくことによります。汗をかけない、かかない人は、暑さに対する体温調節が苦手になりやすいです。この場合には、暑くないような環境で過ごすか、暑くならないような衣服や行動を工夫してください。
A.体温とは
定温動物は、環境の温度変化に関わらずに一定の体温を保ちます。体温を保つために、皮下脂肪を貯えたり、環境変化に対応した体質を作り出します。人間は、この対応能力に個人差や民族性が現れます。同じ体温でも、クーラーの設定温度が、国によってかなり高低差があることで実感します。世界でクーラーの設定が最も高いのが東京で、26.2℃です。バンコク25.1℃、上海25.0℃、パリ23.7℃、ニューデリー23.2℃、ニューヨーク22.4℃、サンパウロ22.2℃、ラゴス(ナイジェリア)21.9℃です(https://www.daikin.co.jp/press/2024/20240725)。外国に行くとクーラーがかなり寒く感じます。日本人は、皮下脂肪が少ないので寒さには弱いのでしょうか。或いは、体温調節機能が強いのでしょうか。人によっても、クーラーへの体感機能はかなり違いがあり、子供や女性や高齢者、そして病人などには注意が必要です。
動物が活動するために適切な体温は37℃前後のようですが、その体温を維持するために定温動物は、多くのエネルギーを必要とします。これが基礎代謝量と結びつきます。爬虫類や両生類は、変温動物と言い、この機能がないので、エネルギーは少なくて済みますが、低温になると活動が衰え、不活発となるので、冬眠などで対処します。日本人の平均体温は、36.2℃とされますが、35℃台の人が増えています。筋肉が少なくて熱の産生が低い人で、寒さにも暑さにも弱くなります。
汗を出す部分は汗腺と呼ばれますが、その数は暑い地域のフィリピン人では280万個、日本人は230万個、ロシア人は190万個あるといわれています。数が少ない程、熱を逃がしにくい身体だと言えます。この汗腺の数は3歳までの育った環境により決まり、暑い環境で過ごせば数が増え、寒い地域で過ごせば数は増えず、寒さに強く、暑さに弱くなります。日本人が寒さに弱いのは「暖かさを溜められない身体」だからとも言えます。日本は古くから高温多湿環境のため、身体が温湿度を溜め込まないつくりになっているのです。
日本では、体温が38℃を超えると「熱がある。」とされます。欧米人の平均体温は37℃以上なので、38℃くらいは通常なようです。日内変動もあり、早朝が最も低く、夕方に最も高くなるようです。子供は、筋肉量や血液量が少なく、体温の上下が急になるので、注意が必要です。身体を正常に保つホメオスタシスは微妙で、体温が36℃を下回ることもあり、代謝が不十分であったり、何らかの原因があったりして、健康の為には対処が必要と思われます。
- 1.平常体温が高めの人
- ① 代謝の良い人は、体温が高い。代謝が高いので太りにくい。
- ② 筋肉は熱を産生するので、筋肉の多い人は体温が高い。
- ③ ストレスなどで交感神経が優位になると体温が高くなる。
- ④ 汗腺が少なく、汗をかきづらい人は体温が高い。
- 2.平常体温が低めの人
- ① エネルギーを作り出すTCAサイクルやATP産生に何らかの障害があると熱の産生効率が悪く、体温が上がらない。
- ② 筋肉が少なく、活動の少ない人は、基礎体温が上がらない。
- ③ 冷暖房などで温度を調整するのに慣れると、身体の体温調整能力が衰えてくる。
- ④ 慢性的な貧血の人は、体内の燃焼に必要な酸素が不足するため体温が上がらない。
- ⑤ 血液の循環が悪い人は、その部位の体温が上がらない。
- ※ 生理などによる低体温と高体温は、その違いを確認しているほうが妊娠や健康には良い。
B.体温が上がる原因とその悪影響
- 1.体温が上がる原因
- ① 活発な運動をすると、代謝が進み、体温が上がる。
- ② ウィルスや細菌などの感染により、その毒素や悪影響で熱が出る。
- ③ 免疫系の働きで、病原体を攻撃するために発熱する。
- ④ ホメオスタシス(恒常性維持)の働きにより、寒くても体温が調整される。
- ⑤ 気温が上がり、ホメオスタシスで対処できなくなると体温が上がる。
- 2.体温が下がらない原因
- ① 水分不足や汗腺が少ないために発汗が十分でない。
- ② 肥満や病気により、身体や血液に十分な水分が貯えられていない。
- ③ 血液やリンパ液の循環が悪い。血液成分が正常でない。
- ④ カリウムなどのミネラルが不足し、腎臓機能が十分に働かない。
- ⑤ 体温調節の自律神経が十分に機能しない。
- ⑥ 身体が対応できる以上に気温や環境が暑い。
- ⑦ 睡眠不足、体調不良、疲れ、体力の衰えなどで、身体の機能が十分に働かない。
- 3.体温が上がり過ぎると身体に悪影響を与える理由
- ① 発熱は、41度を超えると内臓などに害をもたらす。
- ② 脳にも悪影響を与え、頭痛や判断力の低下、精神的混乱をもたらす。
- ③ 汗が増え、血液の水分が不足して濃くなり、脳梗塞や心筋梗塞を起こす。
- ④ 汗が増えて身体のミネラル分が不足し、神経系に異常をもたらす。痙攣や手足のつり。
- ⑤ 皮膚血管の拡張により低血圧をもたらす。
- ⑥ 腎臓疾患の方は、水分や塩分を多く摂ると腎臓に負担を与えることがある。熱中症では、水分が出て血液が濃くなり、また血圧が低くなり、腎臓機能にダメージを与える。
- ⑦ 体温が高くなり過ぎると活性酸素が増えて身体を傷つける。
- ⑧ 発熱しやすい人は体調の変動も急になるので身体が疲弊し、他の病気も併発しやすい。
- 4.熱中症などの高体温の症状
- ① めまい、顔のほてり、頭痛
- ② 筋肉の痙攣、筋肉痛、こむらがえり
- ③ 身体のだるさ、吐き気
- ④ 異常な汗の量、全く汗をかかない。
- ⑤ 判断、反応ができない。ふらふらする。
- 5.熱中症などへの対処法
- ① 涼しい場所に移り、身体を横にし、衣服をゆるめる。
- ② 適切な水分を摂る。
- ③ 首、脇の下、鼠径部など太い血液が通っている個所を冷やす。
- ④ 緊張、硬くなっている筋肉を冷やす。
- ⑤ ツボを押すと身体が楽になることもある。
- ⑥ 病気のある人は軽度の熱中症でも病気が悪化することがあるので、医療機関にかかる。
- ⑦ 高齢者は、症状に気が付かず、対処が遅れることがあるので、周囲のケアが必要。
C.体温調整ができる身体作り
健康な身体づくりは、毎日の努力の積み重ねです。熱中症対策というというよりも、不健康であると、いろいろなストレスなどに身体が対応できないわけです。むろん、健康であっても、無理や無謀な生活や我慢は身体を壊すことになります。肥満、高血圧、膝痛、頻尿、などは、主治医に相談して、日頃から丁寧に対処し、薬に頼る前に身体づくりを心掛けることが大事です。
- ① 体組成計で身体各部の筋肉量や脂肪量、バランスなどを測って自己管理の資料とする。
- ② 運動を欠かさない。筋肉の衰えは、継続的な運動を怠ると直ぐに現れます。
- ③ 温めのお風呂には毎日ゆっくりと入り、血液の循環と発汗を促す。
- ④ 身体全体を動かすことが必要で、凝りはその日のうちに解しておく。
D.体温調整する栄養の補給
食習慣は大事で、野菜嫌い、偏食、揚げ物好き、甘い物好き、麺類好き、大酒、早食い、外食ばかり、夜食習慣、菜食主義なども、その人の健康を損なっていきます。低体温の方は、代謝阻害されている可能性もあります。胃腸障害なども、丁寧に治療することは大事です。また、高齢者は、消化吸収力が衰えてくるので、若い時と同じ栄養の量や質では十分ではありません。
- ① 身体を維持するのに必要なタンパク質量は1.14g×体重(kg)で、高齢者は消化吸収力や再生力が衰えているために1.4×体重(kg)となっています。これが不足すると、生命維持に不可欠でない部位や活動していない部位からタンパク質を分解して補給することになり、身体は衰えていきます。筋肉というのは、最も減りやすい部位であり、最も増えづらい部位なので、筋肉量によって健康度やタンパク質の必要量がわかるのです。
- ② ミネラルは貯えることが難しく、毎日適切な量を補給しなければなりません。カルシウムは生命維持や神経伝達に必須なので、不足すると骨を分解して補給します。鉄もエネルギー代謝に必須ですから、フェリチンとしてタンパク質と結合して細胞内に保存されています。このフェリチンが不足すると鉄分が補給できないために、代謝そして身体の活動に致命的な悪影響をもたらします。カリウムも神経伝達に必須なミネラルですが、汗と共に排出し、不足すると筋肉や心臓に悪影響をもたらします。マグネシウムは代謝に必要で、筋肉や血管の働きに関わり、精神的安定にも必要です。亜鉛は細胞分裂に必須で、老化や活性酸素の悪影響を抑える働きもし、傷の回復や皮膚炎にも必要です。発汗や飲酒によっても排出してしまいます。ナトリウムは、細胞の正常化に必須で、これが不足すると倦怠、めまい、精神的不安定に関わります。発汗によって急激にナトリウムが排出されます。このようにして、ミネラル分の汗による排出は、身体の機能を損ない、体調の悪化に大きく影響するので、十分な補給を心掛けなければなりません。
- ③ 水分の十分な補給は、汗をかかなくても必要です。食事を取る時にも水分は吸収され、代謝によっても水は生成されているので、食事が不足している時は、通常よりも多い水分が必要です。頻尿を恐れて、水分補給を控えると身体全体のホメオスタシスを保てなくなり、血液が濃くなって内臓機能を損なってきます。
- ④ 野菜を摂らないで健康を維持することはできません。偏食や早食い、偏った食習慣が健康を損なうことは間違いありません。
- ⑤ お腹を壊して下痢などをすると腸内環境が悪くなります。免疫力は多くが腸管に関係します。腸内環境が良いと免疫力が高まり、様々な病気のリスクが下げられる可能性があります。発酵食品は腸内環境を健全にします。毎日摂取するようにしてください。
- ⑥ 魚に含まれるEPAやDHAは必須脂肪酸です。必須というのは不足すると健康は保てないということです。酸化しにくいオレイン酸を多く含むオリーブ油も良いです。
執筆者の紹介
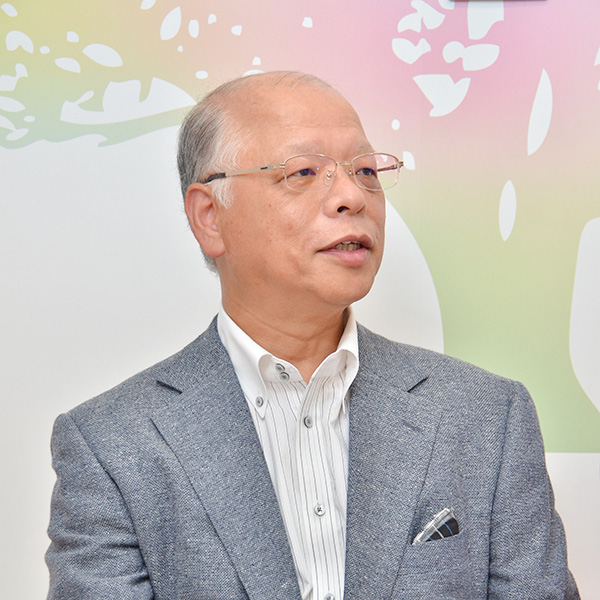
柏崎 久雄
・株式会社ヨーゼフ 代表取締役社長
・マリヤ・クリニック 事務長
・千葉福音キリスト教会 牧師
妻(マリヤ・クリニック院長)が低血糖症なのをきっかけに、分子整合栄養医学を勉強し、2004年にサプリメント会社を設立