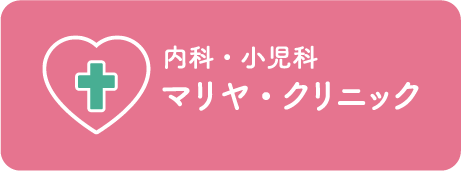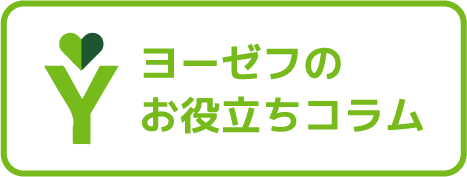ヨーゼフのお役立ちコラム
column
- ホーム
- ヨーゼフのお役立ちコラム
人が死んだ後の手続き
マリヤ・クリニック・ニュース
2025.4. No.360
目次
義姉が亡くなりました。冒頭から申し訳ありませんが、突然の死に呆然としながら、兄は要介護5で何もできないので、代わって葬儀や片付け、手続きを慌てておこないました。
救急車で入院した病院からは、死んでしまったらすぐに移動しなければなりません。葬儀会社に連絡し、その日のうちに葬儀の日取りや次第も決めます。火葬場は混んでいて、早くても8日後でした。
86歳の兄は、介護施設で思い出しては泣いています。80歳の義姉は、まさか自分が死ぬとは思っていなかったのでしょう。独り住まいで片付いてはいましたが、全く準備も記録も残しておりませんでした。親戚と思われる人の住所はわかるのですが、電話番号がわかりません。個人情報保護の観点から、住所から電話番号を探すことはできなくなっています。リンゴ園をやっていたことを思い出し、電話してみると、実兄であることがわかりました。他の連絡先もどうにか探し出して連絡しました。
死後の手続きは、配偶者か直系親族しかできません。役所に届けようとすると、兄の委任状が必要で、何度も行き来しました。その委任状をもらうのに1時間半、委任状を書いてもらって手続きするのに1時間半、その手続きの数の多いことにも途方にくれました。遺産も、子供がいない場合には、配偶者と直系兄弟に分けられますが、その兄弟の一人が死んでいた場合には、その子供たちの了解も必要です。これらは教会員の行政書士に頼みました。
家財も全て処分しなければなりません。これは教会員が、延べ50人くらい何日も掛けて手伝ってくれました。ごみ処理は、夜に夫婦で出向き、何回かで80袋くらいは処理したでしょうか。家具や電化製品の処分は教会員がしてくれました。
葬式は、高名な協力牧師が司式して下さいました。出棺の際は、2階の教会堂から私の息子たちが運び、火葬場には親族等が収骨しました。会葬の食事の席では、義姉の親族と初めての親密な交流をして、その優しさを語り合い、涙を共にしました。生前にできなかったことを悔やむものです。死は、誰にも必ずあるものです。意義ある人生を送った義姉を懐かしむものです。
事務長 柏崎久雄
<人が死んだ後の手続き>
全ての人は、いつかは必ず死ぬことになります。死後の魂については、それぞれの宗教に応じた教えがあり、対応があります。最近の傾向は宗教離れであり、死んだ後のことは考えず、単になくなるものと捉える人が多くなっています。基本的に、宗教は死後の裁きを伝え、人生を如何に過ごしたかによって報いか罰があると教えています。確かに、そのようなことをわきまえて生きる人とそうでない人には、人生に違いがあるように思います。しかし、ここでは、この人生の終わりを迎えた時の手続きを説明いたします。
1. 死の確認
人の死亡を確認できるのは、日本では「医師のみ」です。ですから、どんな場合でも、医師資格を持った人の死亡確認が必要で、「死亡診断書」を書いてもらいます。
- 病院で死ぬ。
医師がいるので問題はありません。
- 自宅で死ぬ。
- 医師を前もって呼んで、死亡を判定してもらいます。
- 医師がいないで死んだ場合には、警察や救急に連絡する必要があります。検死をしてもらい、「死体検案書」を書いてもらいます。この検案書は警察医が書きます。この場合、事件性があると一カ月もかかることがあります。
- 事故などで死ぬ。
「死体検案書」を書く場合が多いです。
2. 遺体の保管
病院では、死亡診断書を書いた後は、速やかに遺体を搬送することを求めます。基本的には、その病院の契約葬儀社が当初の搬出を行い、その後、遺族が指定した葬儀者に引き渡されます。
この時点で、葬儀社と葬儀を執り行う宗教・宗旨、教会や寺を決めておくことが必要です。
3. 親族への連絡
親族に速やかに連絡して、執り行う葬儀や宗教について了解・同意を得ておくことが必要です。喪主が決めてよいことですが、喪主の立場・関係・状態を考慮して葬儀関連の相談と担当する人を確保しておくことが必要です。
経験と判断力のある人がいないと、厄介になる場合があります。喪主以外の人が牛耳ることがないことも必要です。
4. 葬儀の宗教、司式者・僧侶の確認
仏教系の僧侶は葬儀については殆ど関わらず、読経することに専念します。教会は、信者及びその家族に限定されることが殆どですが、丁寧なアドバイスと協力が得られます。最近は、葬儀社に僧侶やお寺を紹介されることが多くあります。
喪主、宗教宗派、僧侶は事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
5. 葬儀社との打ち合わせと葬儀の流れ
葬儀社は、かなり違いがあります。商業ペースで高額な葬儀を契約されてしまうこともあります。宗教性を強調されて、他宗教の人へのその宗教様式の指導もされてしまうこともあります。
遺族が自分たちで葬儀を司り、宗派や教会などに直接お願いすることもありますが、葬儀は急なものなので、葬儀社にある程度依頼したほうが無難であり、順調に準備手配されます。
- ① 火葬場の予約を確認する。
季節によってはなかなか予約が取れず、10日から2週間も待つことがあります。
- ② 通夜、葬式の日程を決める。
火葬場の予約が取れる時間を確認して、葬式の日時を決めます。
通夜(前夜式)は、親族や親しい人が通夜して故人を偲ぶというよりも、故人が仕事をしていた現役世代の場合に来会者の仕事を妨げないように行い、却って葬式よりも人が集まる場合があ ります。両方に参列する人は少なくなっております。 - ③ 参列者の数の予想を伝える。
多いと予想される場合には、会場を変更する場合もあります。
- ④ 会葬御礼の文章作成と品の選定。
会葬御礼の文章は既成のものが多いのですが、私は版代を払って喪主の気持ちを表しました。香典返し(返礼品)は、1,000円から5,000円くらいしますが、参列者の状況を考えて斟酌します。最近は、ご自分で選ぶような目録を用意することが多くなっています。或いは、香典(お花料)を考慮して後日送ることもあります。香典辞退も増えてきました。
- ⑤ 式場作り。
宗教宗派によって異なりますが、葬儀社が用意できます。棺を飾るお花は、遺族が選ばなければなりません。また、生花を受け取るかどうかも決めておかなければなりません。
- ⑥ 係の依頼。
受付は、通常親族から一人、会社などから一人、金額を確認計算管理する人が一人必要です。その他は、葬儀社がやってくれますが、親族から一人応対を担当する人がいると良いでしょう。葬儀でも、手の掛かる人、世話をしなければならない人がいるものです。
- ⑦ 遺体の化粧。
遺体をドライアイスで保存するには、一日1万円以上掛かります。そして、化粧を頼み、似合う服を用意します。現代では、死に装束を着せることは都会では殆どありません。
- ⑧ 火葬場への送迎。
マイクロバスが必要なのか、何人くらい火葬場に行くのか、事前に確認しておく必要があります。
- ⑨ 火葬場での会食の手配。
火葬し収骨をするまでの間に、会食をして待つのが普通です。その食事の手配を前もってしなければなりません。
- ⑩ 収骨。
収骨は、仏教などでは二人で一つの骨を持って骨壺に入れます。キリスト教では、一人ずつ行います。
- ⑪ 納骨。
お墓を用意している場合は、別の日に納骨をします。これは、そのお墓の業者に相談してください。仏教では四十九日法要の日にされるとされますが、現代ではその間、骨壺を自宅等に保管しなければならないので、もっと早くすることが多い様に思われます。納骨には、火葬許可証が必要です。火葬の後に、骨壺を入れる箱に入れてくれます。僧侶に出向いてもらうこともありますが、最近は家族が墓の管理業者に取り扱いを頼むだけのこともあります。お寺にある墓地では、必ず僧侶が立ち会います。服装は、親族は喪服を着ることが多いですが、その他の方は平服でも構わないようです。
6. 葬儀の連絡
親族、職場関係、友人知人に葬儀場と日時、そして喪主を連絡します。そして、できれば通夜、葬式、火葬式にそれぞれ来られるかどうかを聞いてしまったほうが準備がスムーズにいきます。むろん、直ぐにではなく、後でそれぞれの意向をメールなどで伝えてもらうのです。連絡が伝わらず、後から香典などをいただくと、香典返しなど手間が掛ります。誰に伝えるか、まとめてくれる人がいると助かります。
生花などの依頼がある場合には、業者の電話番号などを伝えます。
7. 通夜・前夜式
通夜は仕事が終わって駆け付けられる18時頃から始まり1時間ほどで、その後に通夜振る舞いがあります。親族は一時間前には準備に集まります。そして、流れと役割を確認します。若い人や嫁などはあらかじめ、次第やマナーを調べておくと良いでしょう。葬儀の時に、適宜に動き回るとその後の評判が良くなり、ぼんやりして手伝わないでいると気が利かないと評判が悪くなります。大事なことは、自分の意見は言わずに、年長者や喪主に従うことです。なお、故人の家族は役を担当せず、参列者の挨拶に専念します。最近は、そのようなこともあり、葬儀社に多くを任せるようになりました。
遠方から親族が通夜に参加する場合には、宿泊施設などの紹介もしなければなりません。宿泊費用は自分払いが普通です。駐車場などの確保や案内も必要です。
通夜をしないことも多くなっています。
8. 香典・お花料
外袋には、ご霊前・御玉ぐし料・お花料など宗教によって表書きが違います。
金額は、親族は通夜振る舞いや火葬時の精進落としなどの経費が掛かるのを見越して、金額を増やすことが必要です。親や兄弟は3万円から5万円、友人知人は5千円から1万円、職場の上司は1万円くらい、同僚は3千円から1万円くらいです。前もって案内の時に、香典等を辞退する場合は必要ありません。その場合、返礼品も食事もありません。
9. 葬式
葬式の1時間前には親族は集まります。受付は、来会者に記帳をお願いし、香典を受け取り、返礼品や香典返しを渡します。親族や立場によって座る位置を案内します。
葬式中は、進行に合わせて儀礼をもって対応します。
お焼香は仏教でも宗派によってかなり方法が異なりますが、最近は細かく指導されることはありません。キリスト教では、お焼香の習慣に合わせた献花が行われることもあります。遺族への一礼をして席に戻ります。
飾棺・御花入れは、西洋の例にならって日本でも行われるようになりました。飾られている花をちぎって遺体の周囲に飾り、お別れ或いは死の確認をします。副葬品は、燃やせるものになります。
今回の教会では、故人の写真を音楽付きのエフェクト効果を付けた動画にして待合室や飾棺の際に流して感動を呼びました。DVDにして遺族に贈呈されました。
10. 納骨式
お墓の掃除道具(雑巾、バケツ、ほうき等)とお花を持参します。式の始まる30分以上前には着いて、掃除をしておいて司式者や参列者を迎えます。式後には、茶菓を出して交流します。司式者には謝礼、業者には刻印料、作業料を支払います。納骨式まで、骨壺は自宅などに安置します。
11. その他
その宗教独自の方法、家族葬、その他は、記しません。ただ、故人を偲び、尊ぶ儀礼をすることは、人間として大事なことだと思います。
12. 死亡後の手続き
死亡届(7日以内)、火葬・埋葬許可書、健康保険資格喪失届(14日以内)、介護保険資格喪失届(14日以内)、世帯主変更届(14日以内)、年金受給停止(14日)、葬祭費・埋葬料の請求、準確定申告(4か月以内)、相続税の申告・納付(10か月以内)、相続放棄の申立て(3か月以内)。生命保険の請求、クレジットカード・諸会員の解約、携帯電話の解約など
実体験とキリスト教牧師という立場を基に記しました。至らないこと、或いは他の宗教の方からすれば違っている点もあるかもしれません。死は宗教と密接に結びつきます。その対応は宗教ごとの真摯な思いがあるのです。面倒がらずに、死への備えをしてください。エンディングノートを残しておくのは必須です。
執筆者の紹介
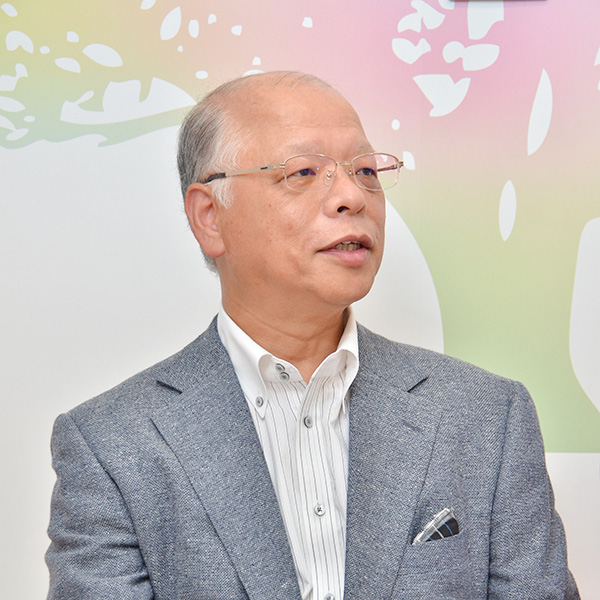
柏崎 久雄
・株式会社ヨーゼフ 代表取締役社長
・マリヤ・クリニック 事務長
・千葉福音キリスト教会 牧師
妻(マリヤ・クリニック院長)が低血糖症なのをきっかけに、分子整合栄養医学を勉強し、2004年にサプリメント会社を設立